目次
・正教会では信徒以外の結婚式をしてくれますか?
・教会ではどんな聖書を用いていますか?
・正教会ではマリヤさまを拝みますか?
・奉神礼(礼拝)で香炉というものが振られるそうですが何ですか?(新着)
・なぜ、大斎
今年はカトリックやプロテスタントのみなさんは4月12日に復活祭を祝いました。でも、その日、世界各地の正教会の聖堂ではシュロや猫ヤナギの枝を手に「聖枝祭」を祝い、イイススのエルサレム入城を記念し、受難週間の開始を告げました。
正教会と他教派で復活祭一致するのは何年かに一度です。
この理由は、正教会が用いている復活祭の決定方式が古代教会の方式をそのまま引き継ぎ、他の教派と異なるからです。
「春分の次の満月後の最初の日曜日」というのが復活祭の日付の決め方の原則ですが、正教会では天文学的な春分ではなく、この決定がなされた第一回全地公会議(ニケヤ)の年(325)の春分の日をユリウス暦上に固定して計算しています。また、ユダヤ教のパスハとともに祝わないという規定(使徒規則7条、アンティオキヤ地方公会規則1条)も守り続け、この二つの要因が複合して他教派の日付と異なるのです。
現在世界の正教会は教会暦に関して、古来のユリウス暦(古代では最も正確な太陽暦)を採用する教会(古暦派)と、近世になってカトリック教会の指導で改められ一般社会やプロテスタント教会にも採用されるようになったグレゴリウス暦を用いる教会(新暦派)とがあります。古暦派では今世紀と来世紀では13日遅れとなっているユリウス暦をグレゴリウス暦上に当てはめて教会暦を定めますので、例えば降誕祭は1月7日(ユリウス暦上の12月25日)となるわけです。ただ、新暦派の教会も、一部の例外(フィンランド正教会)をのぞけば、復活祭とそれに伴う昇天祭や聖神降臨祭(ペンテコステ)という移動祭日に関しては、その計算の基礎にユリウス暦を採用し、古暦派と同じです。なぜなら、グレゴリウス暦をもとに計算すると「ユダヤ教のパスハとともに祝うべからず」という規定が守れない年が出てくるからです。
日本正教会は基本的に古暦派ですが、降誕祭に関しては宣教的な配慮から新暦を採用しています。
正教会の教会暦についてはさらに詳しく知りたい方はhttp://www.goarch.org/access/Companion_to_Orthodox_Church/calendar
![]()
ほんとです。大斎(おおものいみ)といいます。英語ではGreat Lent。
近世まで教会は東西教会いずれもきちんとこれを守っていました。現在、守れるか守れないかは別のことにして、教会が信徒に呼びかけ、信徒自身も守るべきものととらえて、大まじめで取り組んでいるのは正教会だけのようです。
この期間は復活祭の七週間前からはじまります。信徒は特定の食べ物を避け、娯楽や、旅行、宴会が伴うような行事には参加しないように勧められ、逆に平日に行われる「大斎」祈祷に積極的に参加することが呼びかけられます。避けるべき食べ物としては、肉・魚肉・乳製品・たまご製品・酒類(教会の祈りのなかで「ご聖体・血」として分かちあう少量の酒はもちろんOK)です。
いよいよ復活祭となって斎はとかれます。ごちそうをいただき、改めて神さまの恵みに感謝します。
復活祭後の一週間は光明週間とよばれ、逆にふだん規定となっている水曜と金曜の斎もしてはならないとされます。教会は聖神降臨祭までの五十日の復活祭期に入ります。聖堂は純白に飾られ、復活の賛歌が仮に埋葬式であっても高らかに歌われます。
このような斎と祭のメリハリによって信徒は福音をまさにからだで体験するのです
この大斎の精神性については、「大斎の精神性」(「キリスト教をとらえ直してみたい方へ」ページ)を参照下さい
![]()
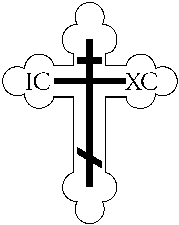 日本正教会はロシヤから伝道されたためロシヤ式十字架(八端十字架といわれます)を用いることが多いのですが、このかたちはスラブ系の教会の伝統にすぎず、ギリシャや他の正教会ではふつうの十字架です。
日本正教会はロシヤから伝道されたためロシヤ式十字架(八端十字架といわれます)を用いることが多いのですが、このかたちはスラブ系の教会の伝統にすぎず、ギリシャや他の正教会ではふつうの十字架です。
さて、まず皆さんに質問させてください。「ハリストスに最初に救われた人は誰ですか?」これがロシヤ十字架のかたちの謎を解くヒントです。…いかがですか。
ロシヤ十字架にはその下部に足台を表す横棒が描かれています。この棒は水平ではなく、十字架上のハリストスから見ると右側に当たる側が上を向き反対側が下がっています。これには意味があります。
ルカ伝が十字架上のハリストスについて次のような出来事を伝えています。
主は二人の強盗とともに十字架につけられました。一人は主の右に、一人は左に。
「十字架にかけられた犯罪人のひとりが、『あなたはハリストス(救世主)ではないか。それなら、自分を救い、またわれわれも救ってみよ』と、イイススに悪口を言いつづけた。もうひとりは、それをたしなめて言った、『おまえは同じ刑を受けていながら、神を恐れないのか。お互は自分のやった事のむくいを受けているのだから、こうなったのは当然だ。しかし、このかたは何も悪いことをしたのではない』。そして言った、『イイススよ、あなたが御国の権威をもっておいでになる時には、わたしを思い出してください』。
イイススは言われた、『よく言っておくが、あなたはきょう、わたしと一緒にパラダイスにいるであろう』」(ルカ23:39-43)
正教会は、この、主を認めて悔い改めた犯罪人は、主の右側の十字架にかけられていた、と言い伝えてきました。そこで、ロシヤ十字架の右上がりはこの悔い改めた「右盗」が主とともにパラダイスに招き入れられたこと、左下がりは悔い改めなかった左の犯罪人が地獄へ落ちたことを表しているのです。
最初に救われたのは、お弟子たちでも、ハリストスの葬りを願い出た勇気あるヨセフ(ルカ23:50)でもなく、この一人の犯罪者でした。彼は、主のために献身したわけでもありません、善い行いで「償い」をしたわけでもありません、愛のわざで貧しい者たちを助けたわけでもありません、ただ生涯の最期にイイススを主であると認め、悔い改めただけです。
正教会の、というより本来のキリスト教の救いに関する教えは、単純明快です。
「悔い改めよ、天国は近づいた(マトフェイ3:2)」…。
悔い改めて神に立ち帰る者は救われるということです。悔い改めない者は救われません。
したがって、クリスチャンの一生は神への立ち帰りの道程です。人間的な弱さで行きつ戻りはあるでしょう、でも、七転び八起き、ハリストスへの信仰と希望と愛を捨て去ることなく、神に近づいて行く人生。終わり無き悔い改めの人生。パスハ「すぎこし」の人生とも言います。
ちなみに上部の横棒は主の罪状書き。
結婚式について
日本のキリスト教界には、カップルの内どちらかが信徒であれば、さらに二人とも信徒でなくても、結婚式をしてくれる教派・教会がたくさんあります。自分の教会より立派な、お菓子の国の宮殿みたいな「チャペル」へ、のこのこ出かけていって、「キリスト教式がステキ!」というカップルに文字通り「サービス」している牧師先生もお見受けするようです。
正教会では、二人とも正教会信徒でなければ結婚式は行いません。結婚式は婚配機密と呼ばれ、「聖体機密」(捉え方は違いますがプロテスタントでの「聖餐」)と同じように洗礼を受けた者だけが受けられる機密(ミステリオン、サクラメント)の一つです。
正教会では結婚は決して個人的な出来事ではなく、信仰によってハリストスに結ばれた新しい家庭が、教会という「神の民」の集いに祝福とよろこびとともに迎えられるという、共同体的な出来事です。よく、西欧の映画や最近の日本のテレビドラマで見受けられる、二人だけがひっそりと司祭や牧師の祝福を受けて結婚し「自分たちだけの」幸せをもとめて二人は旅立つといった結婚を正教会は祝福しません。結婚式には家族や友人はもちろんですが、信徒が大勢集い、美しい聖歌を声をそろえて歌い、ビザンティン時代から少しも変わらない壮麗な儀式を、教会共同体全体が参加する形で行います。断じて結婚するカップルだけの喜びではないのです。
自分たちの結婚と家庭を、ハリストスが十字架と復活という救いのわざによって、この世界にもたらした新しい「いのち」の現実化の場としてささげよう、という二人の自由な決意に、神の祝福と恵みが与えられるのです。そうであれば、互いの信仰の一致が前提であるのは当然でしょう。
福音宣教の手段として、キリスト教に少しでも触れてもらうために、結婚式を未信徒にも開放しようというのは、はっきり言って本末転倒です。
クリスチャンの結婚は宣教の実りであり、手段ではありません。
ある結婚式での説教 正教会の結婚観を知っていただくために
父と子と聖神(聖霊)の名によりて
先ほど、ヨハネによる福音書から、イイススが水をぶどう酒に変えた出来事が読まれました。こんなお話です。
ある日、イイススは、お母さまのマリヤさまとお弟子さんたちといっしょに、カナという町で行われたある人の結婚式にでかけました。大勢の人たちがぶどう酒を飲んだり、ごちそうを食べてお祝いをしていましたが、とうとうぶどう酒がなくなってしまいました。マリヤさまに何とかしてあげて下さいと頼まれたイイススは、その家の僕たちに、そこにあった六つの大きな水がめに水を一杯に入れて、料理を取り仕切っている係の人の所に持っていかせました。料理長がそれをなめてみると、その水は、なんと、おいしい上等のぶどう酒に変わっていました。
教会では、イイススのお弟子さんたちの時代から、結婚式には、このイイススのなさった奇跡が読まれ続けてきました。なぜでしょうか?考えてみて下さい。
答えは、イイススが結婚式でただの水をぶどう酒に変えたということにあります。イイススが祝福する結婚、まさにたった今、お二人がお受けになった恵み。このイイスス・ハリストス、神であるお方の祝福と恵みによって、かつて水がぶどう酒に変わったように、今、お二人の結びつきが新らしいものに変えられたということなんです。
人は誰に教えられなくても、男は女に、女は男に惹かれます。可愛い人だな、ステキな人だな、優しい人だな、頼もしい人だなと胸がときめいて、いっしょになりたいと望むようになります。でも、それだけなら犬や猫だって同じなんです。とてもあやふやなものです。そこで、人類社会は結婚という制度を打ち立てて、このあやふやさを少しでも落ち着いた、社会を安定させるものに変えようとしました。これが結婚です。でも、ただの結婚です。人間のあやふやさを外から押さえつけて何とか、秩序を保とうとしているにすぎません。
このような「ただの結婚」を「ただの男女の結びつき」を、イイススは結婚を祝福することによって、神さまがそもそも人を男と女にお造りになったときに、このようであれとお望みになった姿に、回復されたのです。ただの水が、香しく、美しく、そしておいしいぶどう酒に、飲めば喜びがあふれ、身体を温め、生きる力がみなぎるぶどう酒に変えてくださったように、イイススはただの男と女の結びつきを、いのちを香しく美しくするもの、いのちに喜びと力と栄養を与えるものに変えてくださったのです。
これが、主を信じ、洗礼によって改め造り変えられ、主の結婚の祝福にあずかったお二人に、今、起きたことです。でも、キリスト教は魔法ではありません。神の大きな恵みには人間の努力で応えなければなりません。お二人は、これからの夫婦一体の愛の生活を通じ、今日起きたことを、目に見えるものにしてゆかなければなりません。ぶどう酒も飲まなければただの液体にすぎないのと同じように、今日いただいた恵みを生かす努力を惜しんでは、教会の結婚であっても何もよきものを生み出しません。
最後に、教会は、結婚を個人的な出来事とは考えません。お二人は結婚によって神と教会と隣人にある重大な責任を負う者となりました。
お二人の結婚は、いやすべてのクリスチャンの結婚は、人間を絶望から救うものでなければなりません。人間とはよいものであること、愛というものは幻ではないこと、私たちがどんなに弱く、ねじくれたものであっても、神さまが、イイスス・ハリストスがその私たちをもう一度愛することのできる者たちにしてくれたことを、傷ついた社会に、傷ついた人々に、そして何より傷ついたちいさな弱い人々に、証ししなければならないのです。
アミン。
![]()
日本正教会で使っている聖書
正教会は「旧教」だから旧約聖書だけですか?また、別の聖典をお持ちなんですか?なんて質問をよく受け、どっと疲れてしまうことがありますが、正教会は「キリスト教中のキリスト教」です、新約・旧約とも、もちろん用います。ただ旧約については、紀元前3世紀アレキサンドリヤでヘブライ語原典から72人の学者によって翻訳された「70人訳ギリシャ語聖書(Septuagint)」を用いるのが基本で、他教派と異なります。使徒たちや聖師父たちが親しんだもので、新約聖書の中の旧約聖句の引用はたいていこの聖書からです。使徒たちからの伝統を守るため、正教会は今日に至るまで少なくとも奉神礼(礼拝)においては、70人訳を用い続けています。いわゆる外典については、正典に準じるものとして敬意を払われ、奉神礼でも読まれてきました。ただ、カトリック教会のように「第二正典」という「正典」扱いはしません。
日本正教会では明治時代に語学に大変な才能のあった亜使徒聖ニコライ自らを中心に聖書・祈祷書が翻訳されました。新約についてはその当時の漢文脈の文語体で翻訳された「新約」が出版され、今日でも奉神礼で用いられるばかりではなく、信徒の日々の聖書としても親しまれています。奉神礼で読み上げられ、耳で聞かれることを前提とした、格調高くリズミカルな文体です。旧約は、残念ながら、ひとまとめになったものは、詩編を独立した巻としてまとめた「聖詠経」以外は、出版されていません。ただ、古代から伝えられ今日も生きた伝統として用いられている膨大な祈祷書群の随所に、主要な箇所は翻訳されており、聖歌として歌われたり、誦読されたりしています。
奉神礼以外の、学びの会や日常の読みについては、最近は、文語体には抵抗のある若い人たちを配慮して、聖書協会訳を中心に現代の口語諸訳が用いられることが多くなっています。
日本正教会訳の聖書の入手をご希望の方は、最寄りの正教会にお問い合わせ下さい。
![]()
拝みませんが、讃えます
正教会ではイイススの母マリヤを決して神格化して「拝み」ませんが、生神女(しょうしんじょ)というタイトルを献じ、尊敬し日々の祈りの中、また教会の奉神礼(礼拝)のなかで讃えます。生神女はテオトコス・神を産んだ女という意味のギリシャ語で、古代教会では全教会が用いていた大切なタイトルです。このタイトルに反対する人たち(ネストリウス派・後に中国に渡り「景教」と呼ばれます)が5世紀に現れ、エフェスで開かれた第3回全地公会議で破門されました。神の籍身(受肉)という神が人となられたというキリスト教の根幹にある教義と密接にかかわる大切なタイトルですから、正教会は「聖母」というあいまいなタイトルは好まず、今も生神女と呼び続けます。
ローマ・カトリックの「無原罪の宿り」という考え
さて、正教会がなぜマリヤを讃えるかということですが、決して神格化して讃えているわけではありません。むしろ、ローマ・カトリック教会が近代になって教理として宣言した「マリヤの無原罪の宿り」という考えには強く反対しています。この考えは、マリヤは私たちと異なりその両親から原罪を引き継がずに生まれたというものです。原罪は、正教会的な理解によれば、人類の元祖アダムとエヴァが犯した罪によって人間に生じた、人間性の病・ゆがみですから、このハンデキャップなしにお生まれになったマリヤが、清らかなご生涯を送られたのは当然と言うことになります。(ちなみに原罪という言葉も正教会は西方教会的な法律的理解による原罪観と混同されないよう、なるべく避ける傾向があります。陥罪という表現がよく用いられます)。
普通の人・マリヤ
しかし、それではマリヤは私たち・教会を体現するお方、クリスチャンの生き方の模範ではなくなってしまう、と正教会はこの教理に反対します。正教会の理解では、マリヤは私たちと全く代わらない普通の人として、もちろん原罪というハンディキャップも負ってお生まれになりました。しかし、神の母となる者として、神から特別の恵みを受け、あのような従順と清らかな生涯が可能となりました。これは、私たち自身にも、もし、神の恵みの中で、マリヤのように神のご意志に同意してゆくなら、マリヤの実現した生き方が可能だということです。そして、いまや、クリスチャンは神の恵みの中に生きています。私たちは「神の性質に与る者(ペテロ後書1:4)」になる希望の内にいます。マリヤを「無原罪」とし、普通の人間より優れたお生まれの方とすることは、私たちからこの希望を奪い去ってしまいます。「どだい、生まれが違うんだから俺たちには無理」となるのです。
神が確かに人となられたこと、そしてクリスチャンの「光栄から光栄へ(コリント後書3:18)」の成長の希望のしるしとして、私たちは生神女マリヤを讃え続けます。
香炉・炉儀
正教の奉神礼(礼拝)では「炉儀」がしばしば行われます。「炉儀」は乳香を焚いた振り香炉を、輔祭や司祭が宝座(祭壇)やイコン(聖像)に向かって振ることです。最後には至聖所と聖所を隔てるイコノスタスという仕切の中央にある「王門」といわれる扉の前から、堂内の会衆へも、大きく炉儀されます。なぜでしょう?
私たちの祈りが、かぐわしい香りとして神にとどくように?そうですね。
私たちの心に隠れ潜む悪霊たちを、煙でいぶり出すため?もちろんそういう意味もあります。
しかし、神さまが人間をどのようなものとしてお造りになったかにかかわる、大変重要なもう一つの意味があるのです。
香は、まずハリストスのイコン(像・イメージ)に振られ、生神女から天使や諸聖人のイコンへと深い尊敬を込めて炉儀されていきます。皆、ハリストスによって示された人間の本来のあり方、像(イメージ)を分かちあっているのですから尊敬されるのは当然。そして会衆が炉儀されます。私たちがどんなに弱く罪深くとも、私たちの内に、尊敬されるべき同じ像が宿っているからです。私たちの罪深さにではなく、私たちにひそむ「神の像(イコン)」が炉儀されているのです。
すこし、この機会に正教会の人間の創造についての理解の一端をご紹介します。
神の像と肖
神はまた言われた、「われわれのかたちに、われわれにかたどって人を造り、これに海の魚と、空の鳥と、家畜と、地のすべての獣と、地のすべての這うものとを治めさせよう」。神は自分のかたちに人を創造された。すなわち、神のかたちに創造し、男と女とに創造された(創世記1:26-27)。
創世記は、神の人間の創造をこう伝えます。正教では「われわれのかたちに」を「像・Image」、「われわれにかたどって」を「肖・Likeness」という言葉で表し、神は人間をご自身の像と肖に創造されたと教えます。正教会のほとんどの聖師父は像と肖を全く同じこととは考えません。ダマスクのイオアンは「正教信仰注解」で「『われわれのかたち(像)に』という表現は筋道を立てて物事を考えてゆく力(論理性)と人格的自由をさし、『われわれにかたどって(肖)』という表現は、私たちの霊的努力(徳)によって神に似る者となってゆくことを指す」と言っています。肖は可能性として宿された神の似姿といえるでしょう。
「人がひとりでいるのは良くない」
また「われわれのかたちに創造し、男と女に創造された」とあることは大変重要です。人間は個人としては完全な者ではなく、男と女で、言いかえれば、人格の交わりのなかで初めて完全となる者として造られました。創世記の第二章は、女の創造をもう少し詳しく語りますが、それによると、その発端は神が「人がひとりでいるのは良くない。彼のために、ふさわしい助け手を造ろう(創世記2:7)」とお考えになったことでした。人はひとりでは人ではないのです。
ここで、神がご自身を「われわれ」と呼んでいることに気づいて下さい。この「われわれ」は至聖三者(三位一体)の神のあり方を暗示しています。三位一体の神のあり方、愛による交わりの姿こそ、本来私たち人間がそのように成長してゆかねばならない「神の肖(似姿)」の本質なのです。
肉体と霊の結合
主なる神は土のちりで人を造り、命の息をその鼻に吹きいれられた。そこで人は生きた者となった(創世記2:7)。
人間は、様々な物質が複雑に結合し、その化学反応の連鎖がずば抜けた精神的能力を実現した奇跡的な偶然の産物でも、逆に本来純粋な霊的存在が肉体という「牢獄」に虜になってしまったものでもありません。肉体と霊が結合してはじめて「生きるもの」・人となったのです。人は肉体と霊が健康な調和を保ってはじめて健康と言えます。
神の像と肖・交わりとしての人間・霊と肉体の全体性としての人間、これらは正教会の人間観や救済観の根本にある人間理解です。